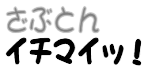書籍「アンダーランド: 記憶、隠喩、禁忌の地下空間」を読んで
以前、バラエティ番組で洞窟探検家という肩書の出演者がでていた。
なんだよ 洞窟探検家 って。〇〇研究家と同じたぐいのもんだな、と当時思った記憶がある。
洞窟と探検というと、あの川口浩探検隊を想起してしまい、胡散臭い印象しかわかない。
本書はその洞窟探検家たちが登場する。
洞窟探検家 は、にわか探検家ではなく、古くから存在し、今も世界各地で活動しているようだ。
また、洞窟探検をホビー的に楽しんでいるものいるらしい。
著者、ロバート・マクファーレンは、本書の著者紹介ではネイチャーライターとなっている。
訳者の力量もあるのだろうが、死と隣合わせの危険な探検を、美しく素晴らしい文体で綴っている。
探検に全く興味のない方(自分も含め)も、読み物として十分楽しめる本だと思う。
500ページを越える分厚い書籍だ。
遅読のσ(^^)だが、なんとか数ヶ月で読破できた。
個人的に印象的だったところを書き記しておく。
第2章 埋葬
1959年、イギリスの洞窟で起きた事件について記されている。
イギリスの洞窟の歴史においてよく知られてた悲劇らしい。
大学生のグループがイギリスはモスにあるピーク洞窟で探検旅行を行った。
しかし、学生の一人が洞窟の狭い部分に挟まり抜け出せなくなる。
洞窟の入り口から800mのところだから、かなり奥まったところでだ。
事件は、イギリス軍までが出動し、全英を揺るがす大事件に発展するが、残念なことに救出に至らず。
建物に閉じ込められたなら、破壊してでも救出するだろうが、洞窟ではそうもいかない。
最終的に彼は洞窟に挟まれたまま、2日後に息を引き取る。
ここの章の描写は、読んでるこちら側も息苦しくなる箇所だった。
遺族の希望により、彼が亡くなった洞窟部分にはコンクリートが流し込まれたらしい。
亡骸が今もなお地底深くにとどまっていると思うと、怖い、可哀そう、というより、不思議な感情が湧いてくる。
そんな危険をはらみながら、それでも洞窟にもぐるのはなぜ?
第3章 ダークマター
前章とうって変わって、著者は地下に作られたダークマターの実験施設を訪れる。
この章で「人新世」という言葉出てくる。
おそらく、このワードを詳しく知ったのは本書が初めてだ。
ご存知の通り、過去や古代のことを研究者は地層から推測している。
地質が氷河の影響を受けた時代を「更新世」、生物繁栄を可能にした時代を「完新世」と呼ぶらしい。
そして、人類が地質の、そして地球の形を変えつつある今を「人新世」と呼ぶことが提唱されているとか。
人類後、知的生物が生まれるなら、この時代をどうみるだろう?
そんな途方も無い未来に思いを馳せさせるワードだ。
第4章 低木層
本章では地下には潜らず、森が舞台となっている。
「ウッド・ワイド・ウェブ」が本章のキーワードだ。
森の中で弱った木があると、他の木がこの木に対して養分を送り、助ける。
その養分の経路になっているのが木の周りに生えている菌類。
この木と菌類の共生ネットワークを「ウッド・ワイド・ウェブ」と呼ぶらしい。
第5章 見えない都市
ヴィクトル・ユゴーの「レ・ミゼラブル」で「パリの下には、もう一つのパリがある」と書かれているらしい。
本章の舞台は、パリの地下に網目のように広がる空洞ネットワークだ。
もともとは、12世紀に行われた石灰石の採掘坑道なのだが、パリの地下の大部分に拡張したようで、一時は地盤沈下で地上の道路や建物が沈む事故が多発したとか。
時代とともに坑道跡は様々な用途に使われる。
18世紀には墓地のキャパから溢れた死体の貯蔵施設として。
19世紀にはキノコの栽培場。
20世紀にはレジスタンスの隠れ処、市民の防空壕として利用された。
芸術の都パリの地下がそんな穴だらけとはなんとも意外だった。
第7章 空虚な土地
筆者はスロベニアの山岳地帯を旅する。
第2次世界大戦、ユーゴスラビアは隣国に侵略され、イタリア、ハンガリー、ドイツに三分割された。
これに反抗するゲリラ舞台が組織され、石灰山岳地帯にできた無数の洞窟を活動場所とした。
もともとは対ファシズムの戦いだったが、共産主義や宗教もからみあい複雑な内戦に発展したようだ。
そして、山岳の陥没穴や洞窟、渓谷にて私的な処刑や集団殺人が行われたが、戦後のこの事実は政治的理由で隠蔽されていたらしい。
東アジアでも、 第2次世界大戦で起きた未解決の事象がいくつかあるが、ヨーロッパでも同様のようだ。
終戦から70年近く立っても、その傷跡が癒えないとは、なんともやりきれない。
第9章 縁
「ソラスタルジア」というワードがでてくる。
「ノスタルジア」は故郷を去る、離れるときに生まれる痛みであり、「ソラスタルジア」はそこに留まりつつも、自分たちの故郷が変えられるときに生まれる痛みらしい。
本章は、石油会社による海底採掘で、漁場を失いつつある漁師町、すなわち環境破壊について記されている。
前述のワード「人新世」と絡めて、「ソラスタルジア」は近年顕著になってきた人の痛み、と語っている。
第12章 隠し場所
フィンランドのオルキオルオト島にある核廃棄物の最終処分場が舞台である。
地下450メートルに使用済みウランが収納されているとのこと。
施設の説明員の熱心な解説に対し、筆者の冷めた心情が綴られている部分がなんとも可笑しい。
「人は未来に保存すためにものを埋めることがある。
また、ものから未来を守るために埋めることもある。
反復と継承を願う埋蔵(貯蔵)もあれば、
忘却を願う埋蔵(廃棄)もある。」
パンドラ箱のごとく、開けちゃダメと言われるほど、人は開けたくなるのが性。
死と対峙しながらも、そんな欲求にかられ、地底を彷徨う。
洞窟探検家というのはそういう人種なのかもしれない。